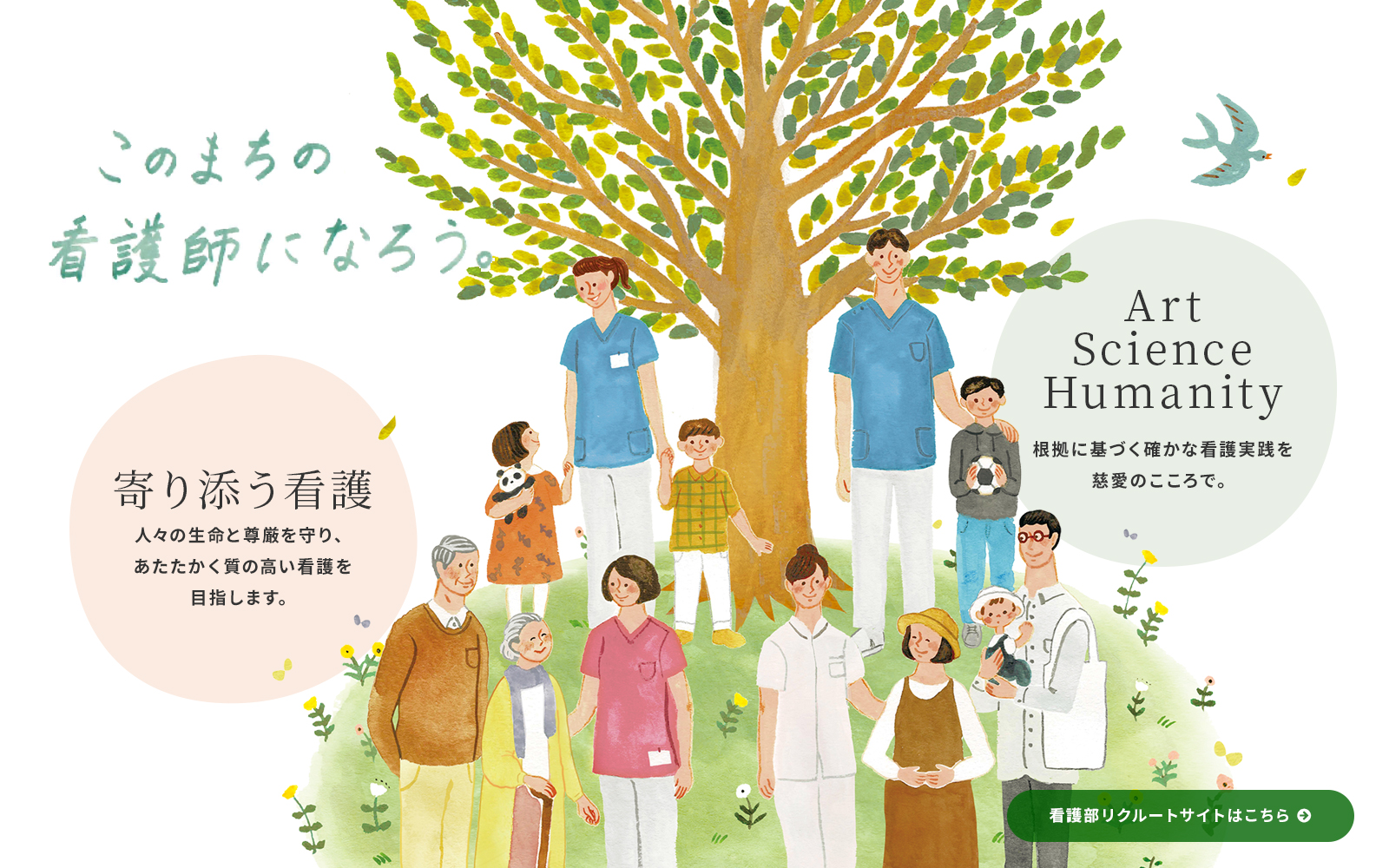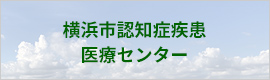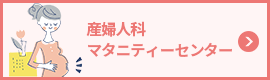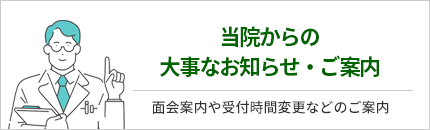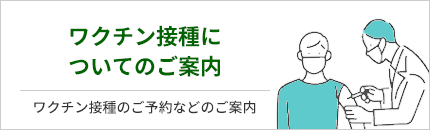選定療養費について
- 2025.05.12 2025年6月1日より 初診時における選定療養費改定のお知らせ 選定療養費
- 2023.11.27 時間外(夜間・休日)選定療養費について 選定療養費
病院広報誌
「プロムナード」のご紹介
よこそうをよりよく知るためのフリーマガジン
プロムナード、院内にて配布中!!
こちらの冊子は通常病院ロビー内のラックに設置しています。
またこちらのホームページからでもPDF版を読むことができますので是非お読みください。
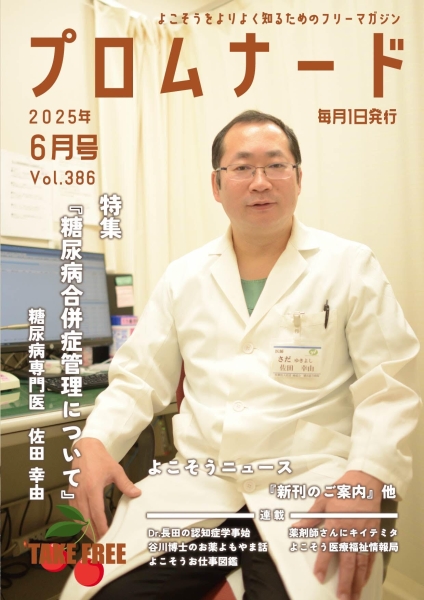
お知らせ
- 2025.06.10 【6月】診療変更のお知らせ 休診
- 2025.06.05 臨床検査技師の募集を開始しました 採用情報
- 2025.06.02 【産婦人科】母親学級・HugHugスクール 6月の予定 患者さんへ
- 2025.06.01 当院の面会条件について(2025.6.1 更新) 大事なお知らせ・ご案内
- 2025.05.30 プロムナード6月号を発行しました イベント・メディア
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
午前 9時00分 - 12時00分 (受付時間 8時00分 - 11時30分) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
午後 14時00分 - 17時00分 (受付時間 13時30分 - 16時00分) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
外来予約センター
平日:9時 - 16時
土曜日:9時 - 12時
(日・祝日 お休み)045-903-7158
歯科口腔外科
直通予約ダイヤル
受付:月~金曜日
14時30分 - 17時045-901-8134
土曜日午後、日曜日、祝日は休診となります。救急受診は24時間、365日受け付けています。詳細は下記『救急および時間外の診療について』をご覧ください。
アクセスのご案内
所在地:神奈川県横浜市青葉区鉄町2201-5
-
お車でお越しの方
国道246号から
- 市ヶ尾交差点より約10分
- 東名横浜青葉ICより約10分
- 東名川崎ICより約15分
ナビゲーションにはこちらを入力
横浜総合病院
青葉区鉄町2201-5
TEL.045-902-0001 -
公共交通機関をご利用の方
電車
東急田園都市線 / 横浜市営地下鉄
あざみ野駅下車小田急線
新百合ヶ丘駅下車バス
あざみ野駅 3番のりば
すすき野団地・虹ヶ丘営業所行
もみの木台下車 徒歩7分新百合ヶ丘駅 9番のりば
あざみ野・あざみ野ガーデンズ行
もみの木台下車 徒歩7分タクシー
あざみ野駅より約10分
病院内タクシーのりばにて待機車両がない場合は院内のタクシー電話よりお呼び下さい。
神奈川都市交通(株)
TEL.045-978-0100 -
病院無料バスをご利用の方
- あざみ野駅
- 青葉台駅
- 鶴川駅/奈良北/こどもの国
- すすき野循環(黒須田/平崎橋/虹ヶ丘)経由
- 麻生循環(麻生台団地/寺家町)経由